勉強についていけず不登校です。現在小学5年生の息子です。できるだけ…
勉強についていけず不登校です。
現在小学5年生の息子です。できるだけわかりやすくしたいので箇条書きで失礼します。
◯母子分離不安の傾向があります。初めての場所や病院などはそばを離れません。
◯勉強についていけない。特に国語と算数。文字を書くのを嫌がります。計算も間違えます。
◯運動会や劇などの行事も嫌がって不参加。先生の手伝いであればやります。
◯これまでに発達障害の診断はなし。グレーゾーンとも言われていません。
◯入学当初より集団に馴染めず不登校気味で、3年生で少人数の現在の学校に転校。
◯3年生の2学期より教室に入れなくなり、別室&母親の付き添いありで登校。
◯4年生から支援級にも席をもらい、一時期付き添いが不要になりましたが、再び別室&付き添いに。
◯別室では支援員の先生と1対1であれば学習は可能(ただし1時間に15分程度が限界)。
◯5年生から支援員の先生が教職免許のない先生に変わり、別室ではずっと遊び。
◯付き添いが私の精神の限界に来たので新学期よりやめたところ不登校になりました。
◯先生や友達と遊ぶのは好きで、休み時間は楽しく過ごしていました。給食も楽しそう。
◯現在は、学校に行くかどうか迷い、結論が出せずに1日が終わる状態です。
本人いわく「学校はとにかくヒマ」で、授業にも行事にも参加しないため学校での時間は「ヒマつぶし」なんだそうです(そりゃそうですよね)。先日、本人に「学校に行きたい気持ちはあるけど、行ったらつらいってことじゃないか?」と聞くと「7割そう」と答えました。
◯私なりの解釈ですが、本人の気持ちとしては、「学校には行きたい。みんなと同じようになりたい。でも、できない。その状態を目の当たりにするのがつらい。」ということではないかと。
◯解決法としては、学校の環境が変わるか、本人の気持ちが変わるかしか無いと私は思っています。学校には相談しましたが、検討の状態が続いています(できないならできないとはっきり言ってほしいのですが、、)。先生も足らず、1対1の対応などは難しいでしょうし、公立の普通の学校ではやはり限界があるのかなと感じています。
◯また、児童精神科に相談していますが、まだ聞き取りの段階で、それも1ヶ月先です(何らかのアドバイスをもらう段階はさらにその先かと・・)
◯本人は何もせず家で動画を見たりゲームばかりしていて、学習を促しても全くやりたがりません。
◯学校の環境を変えるにしても、フリースクールを探すにしても、何かしら改善への指針が無いと動くに動けない状態ではあるのですが、こんな状態で、だらだらと毎日過ごしても良いものでしょうか。
数カ月先であろう病院からアドバイスがもらえる日まで、何かできることは無いのでしょうか。
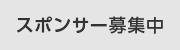
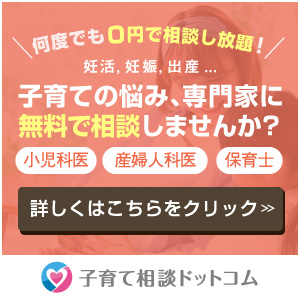















専門家からの回答
こんにちは。お子さんが分離不安や不登校があると、四六時中お母さんと一緒にいることになり、お母さんの負担も大変なものだと思います。
発達障害の診断ができる児童精神科や、学習障害の検査・診断ができる機関は、大変待ち期間が長く、予約しても1年先まで対応してもらえないなどもよくあるようで、いま困っている方への支援が十分ではないのが現状と思います。
不登校・学校が苦痛になる理由は、一見わかりにくいこともあります。子供たちが騒ぐ声が苦痛、時間で区切られて自分でしたいことができないことが苦痛、じっと座っていることが苦痛などの特性から、学校生活になじめない方もおられますが、自分では(それが普通だと思っているから)何が苦痛なのか言うことができない場合もあります。
体験談としてですが、小学校・中学校とも不登校で、お勉強は一切しなかったが、学びたいことが出てきたら、塾などで勉強をして、高卒認定を取って大学に行きましたというような人の体験談もあります。「大学に行くのが良いことだ、最終的に大学に行けるようにならないといけない」と言っているわけではなく、勉強という意味では「不登校だとその後もずっと勉強は追いつけない」ということはないという例です。小学生の脳だと1か月かかって理解することを、高校生の年齢になっていると1日でマスターできるというようなこともあります。知りたい、学びたい、やりたいことがある、そのために勉強が必要だとご自身が気付く、という段階になるまで待たなければならない場合もあります。学習障害などの特性があっても、やりたいことが見つかれば、それに付随する読み書き・コミュニケーション方法を身に付けられることもあります。
学習支援という意味では、
・支援学級がある学校に転校する
・家庭教師を探す(お母さん同席で勉強を見てもらえる、一対一の体制で教えてもらえるため集団の中で一人だけできないなどのプライドが傷つきにくい)
・フリースクールやオルタナティブスクールを探す
といったことが考えられると思います。学校側からは「うちではこれ以上対応できません。転校も考えてください」といったことは申し上げにくいのかもしれませんので、役所の教育担当の部署などに「近隣で支援学級があって対応が得られる学校はどこなのか?」といったご相談をされるのも一つの方法かもしれません。家庭教師やフリースクールはお金がかかりますが、選択肢の一つではあると思います。
世界を広げる、人とのつながりを作る、社会性を身につけるという意味では、ご本人が興味があること、動画やゲームや遊びなどについてでもいいので話し合えるような環境を通じて、同世代の人たちと交流したり、趣味の集まりやサークル、ボランティア活動などにお母さんと一緒に参加する中で様々な背景の方と触れ合うといったこともあるかと思います。同世代だけでいると、視野が狭くなりますが、高齢者や外国にルーツがある方など、様々な人と触れ合うことで視野が広くなる場合もあります。また、お母さんにとっても、不登校や学習障害など様々な悩みを持つ方々の親の回などが参加可能であれば、加わってみて、悩みを共有することで改善する場合もあるかもしれません。
動画やゲームを消費するだけではなく、自分から何か発信する、動画を作って投稿するといった活動から、読み書きやコミュニケーションを学んでいける場合もあります。料理でも家の手伝いでも地域のボランティアでもいいので、自分が何か作り出す、達成する、役目を果たし感謝されるという役割を持てるとよいと思います。
勉強の遅れは、前述のように、きっかけがあれば十分追いつく可能性があると思いますが、学校での標準的なやり方がご本人に合わないだけで、デジタル機器をうまく使うと勉強しやすい場合もあります。手で書くことが不得意でもタブレットのフリック入力・音声入力はできるなどの場合もあります。読むことが不得意なら、読み上げアプリやペン型のスキャナーを使うといったことも考えられます。マルチメディア教科書デイジーといったものもあります。学習障害,LD,読み書き困難、算数障害などで調べると、様々な情報が出てきます。大きい書店の、教育関係の書棚には、学習障害を支援する立場の教師のための指導書や問題集・サポート教材などもございます。ただやはりお母さんが全部するのは大変と思いますし、お母さんが教師役をすることで親子関係が悪化したりする場合もありますので、不登校や学習困難について知識のある支援者とつながりを持てるのが一番よいかと思います。
とても丁寧なご回答、ありがとうございます。
家にいるとどうしても閉鎖的になり悶々としてしまいますが、
相談先を探したり、本人のやりたいこと(勉強でなくても)を探してみたりなど、
少しずつ行動に移してみようと思います。
学習不振については私なりにいろいろ調べたりもしていましたが、
一般的な内容を見ることと、他ならぬ私宛てに書いていただいたものを読むのとでは
やはり印象は違って、とても励みになりました。
お忙しい中ご回答いただき、ありがとうございました。